- 導入(つかみ)
「あれ?この機械、どうして金属をくっつけたりはなしたりできるんだろう?」
「ふつうの磁石って、ずっとくっついてるのに、なんでスイッチでON/OFFできる磁石があるの?」
みなさん、こんな疑問を持ったことありませんか?実はこれ、「電磁石(でんじしゃく)」というとっても便利なもののひみつなんです!今日は、電気の力で動くふしぎな磁石「電磁石」のひみつを、一緒に探検していきましょう。最後には、みなさんも自分だけの電磁石を作れるようになっちゃいますよ!
- 本文(多角的に解説)
その1:実生活の視点「電磁石、どこで使ってる?」
電磁石は、私たちの身の回りのいろんなところで大活躍しています!
· ごみピッキングクレーン
ごみ処理場で、大きな磁石が鉄くずをつかんでいるのを見たことありますか?あれは電磁石。スイッチを入れると鉄をくっつけ、スイッチを切るとパッと離れるから、重い鉄でも楽に運べるんです。
· ベルやブザー
学校のベルや自転車のベルにも電磁石が使われています。電気が流れると鉄片を引きつけて音を出す、というしくみなんですよ。
· ドアホンやインターホン
マンションの玄関のドアを開けるとき、カチッという音がしますよね?あれも電磁石の仕事です。
その2:基本ルールや理論「電磁石の3つのひみつ」
電磁石の強さを決めるのは、次の3つの要素です!
· ひみつ①:鉄心(てっしん)のパワー
電磁石の中心に入れるものを「鉄心」といいます。空気の代わりに鉄の棒を入れると、磁石の力がグンと強くなります。鉄は磁力を通しやすいからなんです。
· ひみつ②:コイルの巻き数
えん線を巻く回数を「巻き数」といいます。巻き数を増やすと、磁石の力も強くなります。たくさん巻くほど、強い磁場ができるからです。
· ひみつ③:電流の強さ
流す電気の量(電流)を増やすと、磁石の力も強くなります。乾電池を2本つなぐと、1本のときより強い力が出せるんです。
その3:心理的アプローチ「失敗しても大成功!」
「うまくできるかな…」と心配な人、大丈夫!
· まずは気軽にトライ!
最初から完璧にできなくてもOK。実験は「やってみる」ことが大事です。
· 失敗は成功のもと
もしうまくいかなくても、それは新しい発見のチャンス!なんでうまくいかないのか考えることで、もっと深く理解できるようになります。
その4:失敗しやすいポイントと対策「これでバッチリ!」
電磁石作りでよくある失敗と、その解決法を教えますね。
· えん線の巻き方
ぐちゃぐちゃに巻くと、電気が流れにくくなります。きれいにそろえて巻くのがコツです。
· 接続の確認
えん線の端の被覆(ひふく)をしっかり取り除かないと、電気が流れません。ニッパーでしっかり切り取りましょう。
· 電池の向き
乾電池の向きを間違えると、思ったような力が出ません。+と-を確認してつなぎましょう。
- 練習問題 or 行動ステップ「電磁石を作って実験!」
さあ、実際に電磁石を作ってみましょう!
【実験:最強の電磁石を作ろう!】
用意するもの:
· えん線(エナメル線)30cm
· 大きな鉄くぎ(10cmくらい)
· 乾電池(単1形または単3形)1〜2本
· クリップや画びょう(くっつけるもの)
· はさみまたはニッパー
作り方:
- えん線を鉄くぎにきれいに巻きつけます(50回くらい)
- えん線の両端の被覆を1cmほどはがします
- はがした部分を乾電池の+極と-極につなぎます
実験のやり方:
- 電池をつなぐ前に、鉄くぎがクリップを引きつけるか試してみよう
- 電池をつなげたら、今度はクリップがくっつくか試してみよう
- 巻き数を増やしたり、乾電池を2本にしたりして、くっつくクリップの数がどう変わるか調べてみよう
結果の例:
· 巻き数50回、乾電池1本:クリップ3個くっついた
· 巻き数100回、乾電池1本:クリップ6個くっついた
· 巻き数100回、乾電池2本:クリップ10個くっついた
どうですか?巻き数を増やしたり、乾電池を増やしたりすると、くっつくクリップの数が増えましたか?
- まとめ
今日学んだことを振り返ってみましょう!
· 電磁石は スイッチでON/OFFできる便利な磁石
· 強さを決めるのは 鉄心・巻き数・電流の3つ
· 実験のコツは きれいに巻く・しっかり接続・電池の向き確認
· 大切なのは 楽しみながら挑戦すること!
次にできる小さな一歩:
今度は、くぎの代わりに別のものを使ってみましょう。例えば、プラスチックの棒や木の棒で試してみると、どんな結果になるかな?新しい発見があるかもしれませんね!
電磁石のひみつ、とっても面白かったでしょ?また一緒に科学の探検をしようね!

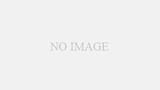
コメント