- 導入(つかみ)
「重い石を動かしたいのに、全然動かない!」
「缶ジュースのふた、固くて開けられないよー」
「はさみで厚い紙を切るの、すごく力がいるなあ」
みなさん、こんなことで困ったことありませんか?実はこれ、全部「てこの原理」を使えば、とってもラクに解決できちゃうんです!今日は、小さな力で大きなものを動かすふしぎなパワー「てこ」のひみつを、一緒に探検していきましょう。このひみつがわかると、毎日の生活がもっと便利になっちゃいますよ!
- 本文(多角的に解説)
その1:実生活の視点「てこ、どこにでもあるよ!」
てこは、私たちの身の回りにたくさんかくれています。
· はさみや缶切り
はさみは指で握る部分が力点、回すところが支点、物を切る部分が作用点です。小さな力で厚い紙も切れちゃうんです!
· てんびん棒
昔の人が水を運ぶのに使っていたてんびん棒。肩が支点で、両端のバケツが作用点。バランスよく持つと、重い水もラクに運べます。
· シーソー
公園のシーソーは、真ん中の台が支点。軽い人と重い人がうまく遊ぶには、支点からの距離を変えればいいんですよ。
その2:基本ルールや理論「てこの3つのポイント」
てこを理解するには、3つの重要な点をおさえよう!
· ポイント①:支点(してん)
てこが回転する中心の点です。「支える点」だから支点。シーソーの真ん中の台、はさみの留め具の部分が支点です。
· ポイント②:力点(りきてん)
力を加える点です。はさみなら指を入れる部分、栓抜きなら手で持つ部分が力点です。
· ポイント③:作用点(さようてん)
力がはたらく点です。はさみなら物を切る刃の部分、栓抜きなら瓶のふたにかかる部分が作用点です。
てこの黄金ルール:
「支点から力点までの距離 × 力」=「支点から作用点までの距離 × 重さ」
つまり、力点を支点から遠くすればするほど、小さな力で重いものが動かせるんです!
その3:心理的アプローチ「むずかしく考えないで!」
「3つの点って、ごちゃごちゃしそう…」と思った人、安心してください。
· まずはイメージしよう!
実際に身の回りのもので考えてみると、とっても簡単です。
· 間違えても大丈夫
最初はどれがどの点かわからなくてもOK。何回かやってるうちに、自然にわかってきます。
その4:失敗しやすいポイントと対策「うまくいくコツ」
てこの原理を使う時に気をつけることを教えるね!
· 支点を見つけよう
まずは「どこの点を中心に回っているか」を考えてみよう。そこが支点です。
· 距離をしっかり計ろう
支点からの距離が大事。ものさしで正確にはかってみよう。
· 力を入れる方向に注意
てこを動かす時は、まっすぐ下に力を入れるときれいに動くよ。
- 練習問題 or 行動ステップ「てこ博士になろう!」
実際に身の回りのものでてこの原理を確かめてみよう!
【実験:身近なものでてこを体験!】
用意するもの:
· 定規(30cm)
· 消しゴム
· 10円玉数枚
· ペンや小さいおもり
やり方:
- 消しゴムを机に置いて、その上に定規の15cmのところをのせます(これが支点)
- 定規の一端(例えば5cmのところ)に10円玉を5枚のせます
- もう一方の端(例えば25cmのところ)に、指で軽く押してつり合うか試してみます
- 10円玉の枚数を変えたり、支点からの距離を変えたりして実験
もっとやってみよう:
· 瓶のふたを開ける時、普通に開けるのと、タオルを巻いて開けるのと、どちらがラク?
· ドアの取っ手を、端の方持つとラク?真ん中持つとラク?
結果の例:
· 支点から遠くで力を加えるほど、小さな力で重いものが動かせる
· タオルを巻くと、支点から力点までの距離が長くなるからラク
· ドアの取っ手は端の方を持つ方がラク
- まとめ
今日の発見をまとめてみよう!
· てこには 支点・力点・作用点の3つの点がある
· てこのルール 力点を支点から遠くすると小さな力で重いものが動かせる
· 身の回りに はさみ、栓抜き、シーソーなど、てこがいっぱい!
· 大切なのは まずは実際にやってみること
次にできる小さな一歩:
今度、何か重いものを持ち上げる時や、固いふたを開ける時、「てこの原理が使えないかな?」と考えてみてください。もっとラクな方法が見つかるかもしれません!
てこのひみつ、とっても面白かったでしょ?また一緒に科学の探検をしようね!

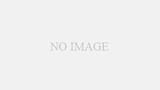
コメント