1. 導入(つかみ)
「俳句とか短歌って、なんかむずかしい…」
国語の授業でそう思ったことない?
文字数は少ないのに「作者の気持ちを考えなさい」って言われると、「そんなのわからんよ!」ってなっちゃうよね。
でも実は、詩・短歌・俳句には「季語」と「比喩」という、わかると一気に楽しくなる“カギ”が隠れているんだ。
今日はその2つを、一緒に探っていこう!
2. 本文(多角的に解説)
① 実生活の視点:季語や比喩は「日常の魔法」
たとえば、春に「桜」と聞いたらどう?
「入学式」「お花見」「あったかい風」ってイメージが浮かんでくるよね。
これが季語の力。たった一言で季節の空気を呼び出せるんだ。
一方で比喩は「言葉の魔法」。
友だちに「今日のカレー、火山みたいにアツアツ!」って言われたら、すぐイメージできるよね。
そんなふうに、日常の言葉にも使えるトリックなんだよ。
② 基本ルールや理論:知っておきたいポイント
① 季語ってなに?
季節を表す言葉のこと。 俳句では必ず一つ入れるのがルール。 例:春=桜、夏=蝉、秋=紅葉、冬=雪。
② 比喩ってなに?
何かを別のものにたとえる表現。 「〜のようだ」と言う「直喩(ちょくゆ)」、 言葉を省いてスパッとたとえる「隠喩(いんゆ)」があるよ。
📖 例:
「月がランプのように夜を照らす」=直喩
「月は夜のランプだ」=隠喩
③ 心理的アプローチ:ゲーム感覚で楽しむ
季語さがしゲーム:新聞やテレビを見て「季節を表す言葉」を見つけてノートにメモ。 比喩つくりゲーム:今日の給食や友だちを何かにたとえてみる。 例:「プリンは宝石みたいにツルツル」
勉強だと思うと大変だけど、ゲームだと思えば楽しくできるよ!
④ 失敗しやすいポイントと対策
✅ 失敗1:季語をただの季節の言葉として終わらせる
→ 季語は「雰囲気の合図」。桜=春、だけじゃなく「新しい始まりの気分」も表してるんだ。
✅ 失敗2:比喩を見つけても、気持ちを考えない
→ 「たとえてるな」で終わらず、「どういう気持ちを強めたいのか?」まで考えると点数アップ!
✅ 失敗3:むずかしい表現を無理に探す
→ 短い言葉だからこそ、シンプルな解釈で大丈夫。
⑤ 他人の工夫例:俳句ノート
あるクラスでは、俳句を読むたびに「季語マーク」と「比喩マーク」を色分けしてノートに書き込むんだって。
青=季語、赤=比喩、って感じで。
そうすると「この句は季語が秋だから雰囲気がしんみり」「比喩で強調してるから生き生きしてる」ってすぐ見えるんだ。
3. 練習問題(やってみよう!)
次の作品を読んで、「季語」と「比喩」を探してみよう。
①
「古池や 蛙飛び込む 水の音」
👉 季語は?比喩はある?
✅ 答え:季語=蛙(春)。比喩はなし。でも「ぽちゃん」という音から静けさと動きの対比が感じられる。
②
「雪だるま まるで友だち 待っている」
👉 季語は?比喩は?
✅ 答え:季語=雪(冬)。比喩=「まるで友だち」という直喩。雪だるまを人みたいに表している。
③
「夏の夜 花火は星の 子どもたち」
👉 季語は?比喩は?
✅ 答え:季語=花火(夏)。比喩=「花火=星の子どもたち」という隠喩。花火を夜空の星とつなげている。
4. まとめ
今日は「季語」と「比喩」という、詩・短歌・俳句を楽しむ2つのカギを学んだね。
季語は「季節の空気を呼び出す言葉」 比喩は「言葉の魔法でイメージを広げる工夫」 ゲーム感覚で探すと、国語がもっと面白くなる 解釈はシンプルでOK。大切なのは「自分の感じ方」
👉 次の一歩は、教科書や家の周りの自然を見て「季語」や「比喩」をメモしてみること。1日1つでいいから集めると、自分だけの“言葉の宝箱”になるよ。
俳句や短歌は短いけど、その中にギュッと季節や気持ちがつまってる。
今日からちょっとした探偵気分で、言葉のひみつを見つけてみよう!

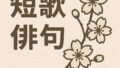
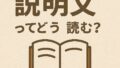
コメント