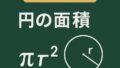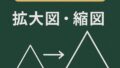1. 導入(つかみ)
「箱をばらばらにして平らにできたら、どうなるんだろう?」
「このピザ箱の形を紙に写したら、全部の面が見えるかな?」
こんなふうに考えたこと、あるよね。
算数でいう 立体の展開図 は、まさにこのイメージ。
立体を紙の上に広げて、「どの面がどこにあるか」をわかりやすくした図のことなんだ。
覚えると、工作や箱の設計、お菓子のパッケージ作りにも役立つんだよ。
今日は、角柱や円柱、立方体などを使って、展開図を楽しく学んでいこう!
2. 本文(多角的に解説)
① 実生活の視点:身近な立体と展開図
立方体:サイコロ、積み木、立方形の箱 角柱:牛乳パック、チョコの箱 円柱:ジュースの缶、トイレットペーパーの芯
たとえばジュースの缶を紙で包むとき、展開図を知っていると「どの面をどこに置くか」がすぐわかるよ。
工作や折り紙でも展開図は大活躍!
② 基本ルールや理論
立方体の展開図
立方体には6つの面があるから、展開図も6つの正方形になるよ。
面をどの順番でつなげるかで、いろんな形が作れる 覚え方のコツ:1枚の面から順番に横や上に広げるイメージ
角柱の展開図
角柱は、上面・底面・側面(長方形が4枚)
側面を1列に並べて、上と底をくっつける 牛乳パックをばらしたら展開図の形になるよ
円柱の展開図
円柱は、上面と底面(円)+側面(長方形のように丸める部分)
側面を切り開くと長方形になる 円の周の長さ=長方形の横の長さ、高さ=長方形の縦
展開図のルールは、「立体を切って広げると面になる」ということ。
紙に描くときも、順番に広げてつなげるとラクになるよ。
③ 心理的アプローチ:楽しく学ぶコツ
立体を実際に折ったり切ったりしてみる 色ペンで面ごとに色を変えると見やすい 展開図を「パズル」と考えるとゲーム感覚で覚えられる
例えば、家にある牛乳パックを切り開いて展開図を作ると、算数がぐっと身近になるよ。
④ 失敗しやすいポイントと対策
面の数をまちがえる → 立方体は6面、角柱は底2枚+側面4枚、円柱は底2枚+側面1枚 面の順番を間違える → 展開図は「折ったら元の形に戻る順番」で描く 側面の長さ・円周を間違える(円柱) → 側面の長さ=円周、縦の長さ=高さ
⑤ 他人の工夫例・応用の仕方
お菓子のパッケージデザインで展開図を使う 工作で「自分だけの立体」を作る 箱を作るとき、紙のサイズを考える
工作や実生活と結びつけると、算数の勉強がもっと楽しくなるよ。
3. 練習問題(やってみよう!)
問題1(立方体)
1辺3cmの立方体の展開図を描こう。
ヒント:正方形を6枚、順番に広げる
問題2(角柱)
底面が縦4cm×横2cm、高さ6cmの角柱の展開図を描こう。
側面は長方形4枚、上面と底面は長方形じゃなくて底面と同じ形
問題3(円柱)
半径2cm、高さ5cmの円柱の展開図を描こう。
側面は長方形、長さ=円周、縦=高さ
問題4(応用)
ペットボトル型の円柱を切り開いて、展開図に色を塗ってみよう。
上下の円は青、側面は赤にして折ったら元の形に戻るか試してみよう
4. まとめ
展開図は「立体を切って広げた図」 立方体:6枚の正方形、角柱:底2枚+側面4枚、円柱:底2枚+側面1枚 紙に描くときは「折りたたむ順番」を意識する 工作や生活の中で実際に作ってみると理解がぐっと深まる