1. 導入(つかみ)
「説明文って、なんか眠くなるんだよなぁ……」
そう思ったことない? 物語は楽しいのに、説明文は「読まされてる感」がある。テストになると「この文章の筆者の考えを答えなさい」とか言われて、なんだかめんどくさい。
でもね、説明文ってちょっとしたコツを知ると、一気に“謎解きゲーム”みたいに読めるようになるんだ。しかも、そのコツはたった3つ!
それが 「比較」「因果」「具体例」 だよ。
この3つを見つけられるようになると、「あ、ここが筆者の言いたいことか!」って分かるようになるんだ。
今日はそのコツを、友達に教えるみたいに楽しく説明していくね。
2. 本文(多角的に解説)
(1)実生活の視点:身近な場面で考えてみよう
例えば、友達と「どっちのゲームがおもしろい?」って話すとき。
Aのゲームは絵がきれい。 Bのゲームはストーリーが深い。
これってもう 比較 だよね。「どっちがどうちがうのか」を並べることで、話が分かりやすくなるんだ。
また、「昨日ゲームやりすぎて寝不足になったから、今日は眠い」ってのは 因果。原因と結果をつなげている。
さらに「Aのゲームは、ドラゴンを倒すと宝箱が出てきて、武器が手に入るんだ!」って言えば、具体的なシーンを思い浮かべられるよね。これが 具体例 だ。
つまり説明文って、普段友達としゃべってるのと同じ仕組みでできてるんだよ。
(2)基本ルールや理論:文章のしくみを知ろう
説明文の作者は、「自分の考えをわかりやすく伝えたい!」と思って文章を書いている。
そのときよく使われるのが、この3つ。
比較:「〜と比べると」「〜に対して」「一方で」 因果:「だから」「そのため」「〜が原因で」 具体例:「例えば」「たとえば」「〜のように」
こういう言葉を見つけたら、「あ、ここ大事なポイントだな」って思えばOK。
(3)心理的アプローチ:楽しく読むコツ
説明文を「暗号解き」だと思うと楽しくなるよ。
「この筆者はどんな秘密のメッセージを隠しているのかな?」って気持ちで読むと、眠気が吹き飛ぶ!
例えば、「比較の言葉」を見つけたらメモ帳に「vs」って書いてみる。
「因果の言葉」を見つけたら「→」って書く。
「具体例」が出たら「☆」マーク。
こんなふうに印をつけて読むと、文章の地図ができあがって、読解がめちゃくちゃラクになるんだ。
(4)失敗しやすいポイントと対策
よくあるミスは、
具体例を「筆者の考え」だと思ってしまう 比較の部分だけ読んで、どっちがいいと言いたいのか見逃す 因果の関係を逆にしてしまう
例えば「スマホを長時間使うと、目が悪くなる」と書いてあったら、
「目が悪いからスマホを使う」じゃないよね。因果が逆になっちゃう。
対策はかんたん。
具体例の後には「だから筆者は何を言いたい?」を考える 比較は「結局どっちを推してる?」を確認する 因果は「どっちが原因?どっちが結果?」をチェック
これを意識するだけでミスは激減するよ。
3. 練習問題 or 行動ステップ
じゃあ、さっそく練習してみよう!
【練習問題】
次の文を読んで、(A)(B)(C)が「比較」「因果」「具体例」のどれに当たるか答えてみてね。
(文章)
図書館で本を借りるとき、家で読むのとはちがった気分になります。(A)図書館には静かな雰囲気があり、それが集中を生み出すからです。(B)たとえば、同じ小説を家で読むよりも、図書館の方が一気に読み進められることがあります。(C)
【答え】
(A)→ 因果 (B)→ 具体例 (C)→ 比較
どう? 意外とできちゃったでしょ。
【今日からできる行動】
学校の国語の説明文で、「例えば」「だから」「一方で」を探してみる。 見つけたら、教科書の横にマーク(☆、→、vs)をつける。 「筆者は何を言いたいのか?」を1行でメモしてみる。
これをやるだけで、説明文のテストがかなり楽になるよ。
4. まとめ
比較=ちがいをくらべて分かりやすくする 因果=原因と結果をつなげる 具体例=「例えば〜」でイメージしやすくする
この3つを見つけるだけで、説明文は「ただの文字のかたまり」から「意味のある地図」に変わるんだ。
次に説明文を読むときは、探偵になった気分で「比較・因果・具体例」を探してみてね。
そしたら「なんだ、説明文ってけっこう楽しいじゃん!」って思えるはず。
👉 さぁ、今日から国語の授業で「暗号解き」を試してみよう!


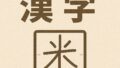
コメント