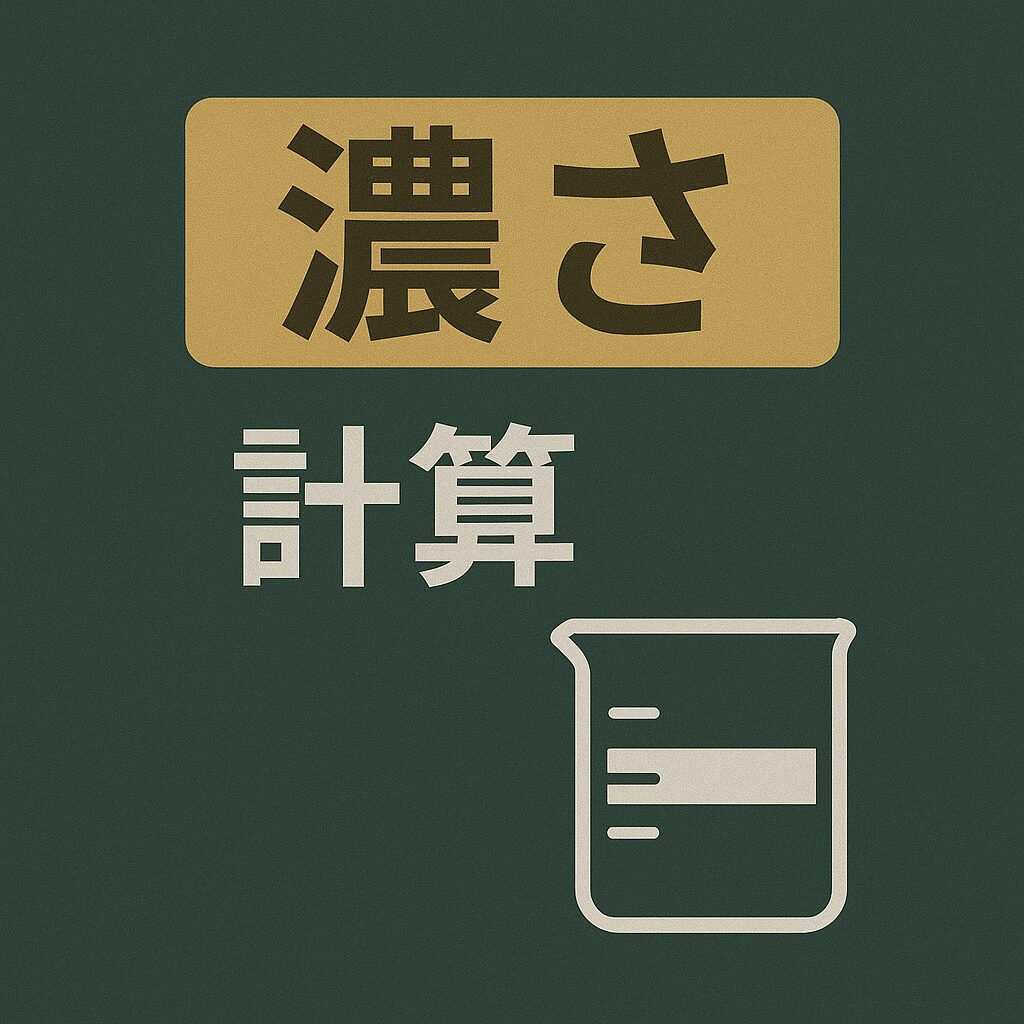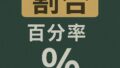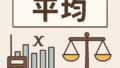1. 導入(つかみ)
ねえ、ジュースを作ったときに「ちょっと甘すぎた!」とか「薄すぎて味がしない!」ってこと、ない?
実はそれ、濃さの問題なんだよ。
学校の算数では「食塩水の濃さを求める」っていう問題が出てくるんだけど、これがまた「ややこしい〜!」って思う子が多いんだよね。
でも安心して。
食塩水の濃さって、考え方さえつかめばパズルみたいにスッキリ解けるんだ。
今日はその秘密を、先生っぽく、でも友達っぽく(笑)やさしく教えるよ。
2. 本文(多角的に解説)
① 実生活の視点:食塩水は身近にある!
「食塩水」って聞くと、なんだか理科室にありそうなビーカーを思い浮かべるかもしれないね。
でも実は、ふつうの生活の中にもあるんだよ。
味噌汁やスープ → 塩の量とお湯の量で味が変わる スポーツドリンク → 実は「ちょうどいい濃さ」に計算されている 漬物や梅干し → 塩の濃さでしょっぱさが変わる
つまり「濃さ」って、毎日の生活にめちゃくちゃ関わっているんだ。
だから算数の「食塩水の利用問題」は、ただの計算じゃなくて、暮らしに直結してるってこと!
② 基本ルールや理論:濃さの公式をおさえよう
ここからちょっと先生っぽくなるけど、ついてきてね。
食塩水の濃さは しおの重さ ÷ 全体の重さ × 100(%) で求められるよ。
濃さ(%) = \frac{食塩の重さ}{全体の重さ} × 100
例:
100gの水に10gの塩を入れると…
全体の重さは「100 + 10 = 110g」
濃さは「10 ÷ 110 × 100 = 約9%」
「へぇ〜なるほど!」ってなった?
これを覚えると、利用問題でも迷わなくなるんだ。
③ 心理的アプローチ:ゲーム感覚でやってみよう
食塩水の問題って「数字ばっかりでつまらない」って思う子もいるかもしれない。
そこでおすすめは、ゲーム感覚で考えること!
自分を「シェフ」だと思って、ちょうどいいスープを作る気分で計算する 好きなジュースに「シロップを混ぜすぎたらどうなる?」ってイメージする 実際に家で「塩を入れて味見」してみる
こうやって「おいしい味を作る」みたいに考えると、数字のやりとりも楽しくなるよ。
④ 失敗しやすいポイントと対策
さて、ここでありがちな失敗もチェックしておこう。
全体の重さを忘れる → 「水の重さだけ」で計算しちゃう子が多い!必ず「水+塩」を忘れないこと。 %を出すときに×100を忘れる → 小数のまま止めちゃうと「正解まであと一歩」で悔しい!最後まで計算しよう。 混ぜたときの全体量を考え忘れる → 10%の食塩水100gと5%の食塩水100gを混ぜたら…全体は200gになるよね?ここを忘れる子が多いんだ。
対策はシンプル。
「全体・食塩・濃さ」この3つをセットで考えること!
表にまとめたり、ノートに図を書くとミスが減るよ。
3. 練習問題にチャレンジ!
さあ、ここまで読んだら試してみよう!
問題1
5%の食塩水200gに、食塩を10gとかすと、何%の食塩水になる?
問題2
10%の食塩水100gと20%の食塩水200gを混ぜると、何%の食塩水になる?
解答・解説
問題1の解答
5%の食塩水200gには、
200 × 0.05 = 10g の食塩が入っている。
ここに食塩10gを追加 → 合計20g。
全体は200 + 10 = 210g。
20 ÷ 210 × 100 ≒ 9.5%
問題2の解答
10%の食塩水100g → 食塩10g
20%の食塩水200g → 食塩40g
合計 → 食塩50g、全体300g
50 ÷ 300 × 100 = 16.6%(約17%)
4. まとめ
今日は「食塩水の濃さ」について、
身近な生活の例 濃さの公式 楽しむ工夫 失敗ポイントと対策 を見てきたよ。
「濃さ」って聞くとむずかしそうだけど、考え方はシンプル。
全体・食塩・濃さの3つの関係をおさえれば大丈夫!
次の一歩としては、今日の練習問題みたいに「混ぜる・足す・引く」のバリエーションを少しずつやってみよう。
そうすれば、算数のテストで「おっ、出たな!」ってにやりとできるはず。
算数は敵じゃなくて、味方にしちゃえばこっちのものだよ!